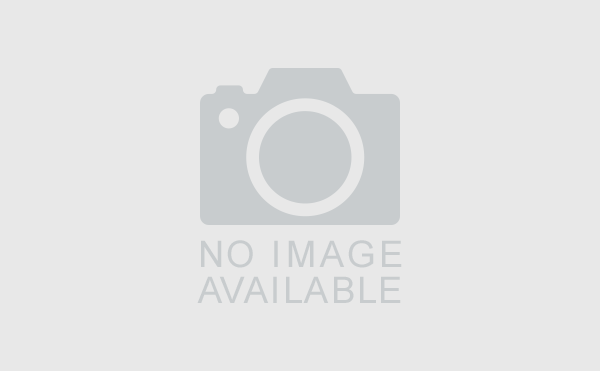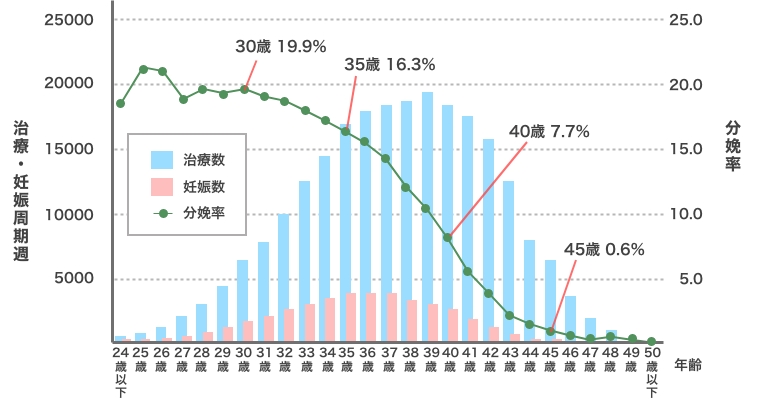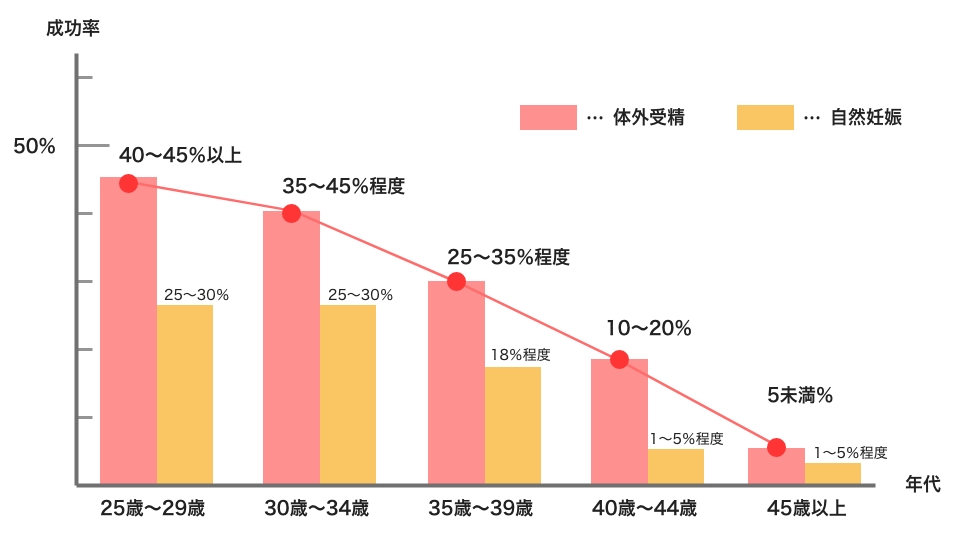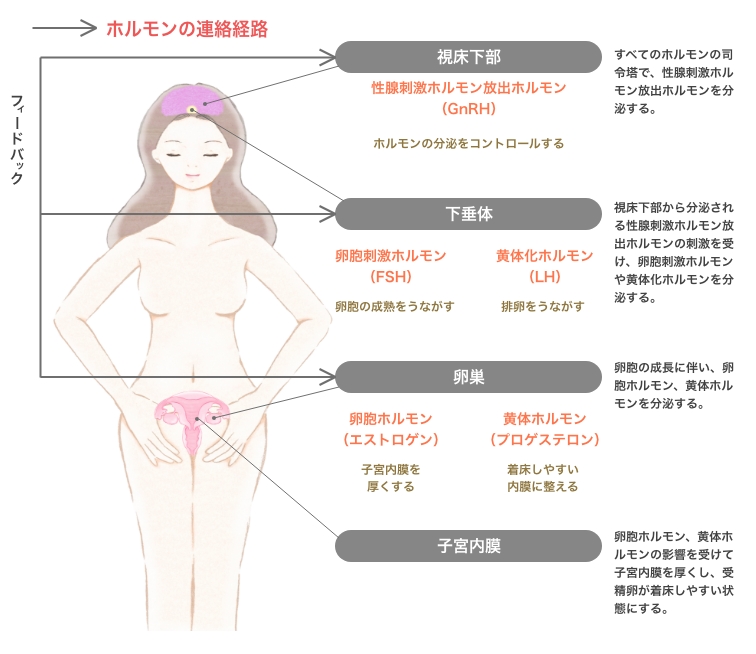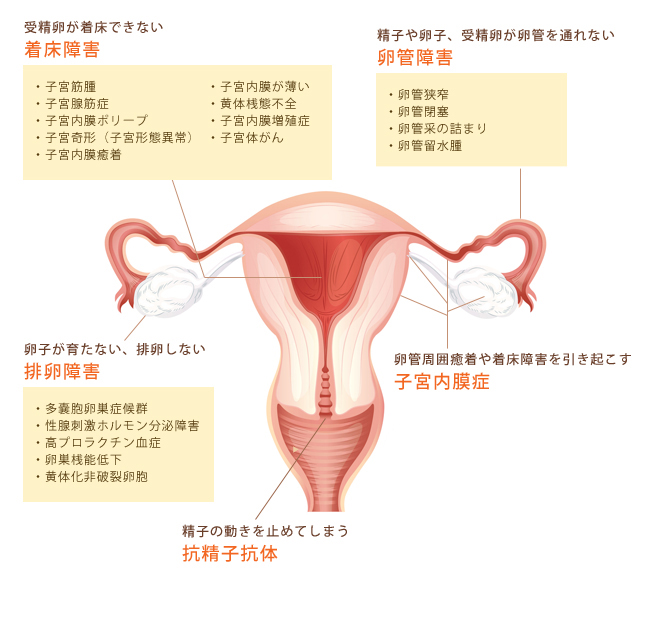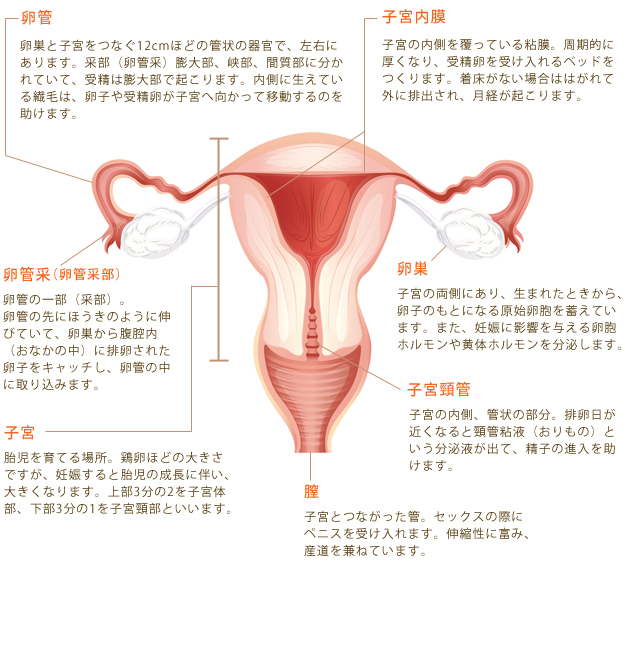不妊治療を考える 40年前の高度生殖医療
現在、多くの方が受けている高度生殖医療(体外受精・顕微授精)の歴史は50年近くになります。
1978年に世界初の体外受精成功、1992年には顕微授精が成功しました。
日本では1983年に体外受精児が誕生し、1992年に顕微授精による赤ちゃんが誕生しています。
その頃の高度生殖医療は現在のものとはかけ離れていました。
排卵誘発剤による卵巣刺激で多くの卵子を採卵し、受精させます。
まだ胚の凍結技術がありませんので、受精した胚を採卵2日~3日後にすべて移植します。
採卵前日に入院し、受精確認の数日後に移植を行うわけです。
移植後は腰を45度ほどの角度に固定して、6~8時間ほどベッドの上から動くことができません。
トイレに行けないので排尿の近い人はオムツをして過ごします。
入院して、手術室で麻酔をして採卵し、数日後に移植する過程は大掛かりなものでした。
多数の胚を移植するため、多胎児を妊娠される方もおりメディアなどに五つ子ちゃん、六つ子ちゃん
などの報道を記憶されている方もいらっしゃるでしょう。
現在は、通常移植する胚は一つです。2個同時移植や二段階移植なども行いますが、多数の胚を移植する
ことは胎児にも母体にも負担が大きいため行われていません。
現在の不妊治療、高度生殖医療は目覚ましい進歩を遂げています。
それゆえに多くの問題もはらんではおりますが、挙児を希望される方々には大きな光明であります。
この妊活コラムでは、不妊治療の基礎的なことを綴ってまいりました。
これからは「高度生殖医療」にスポットを当てて、考えていきたいと思います。