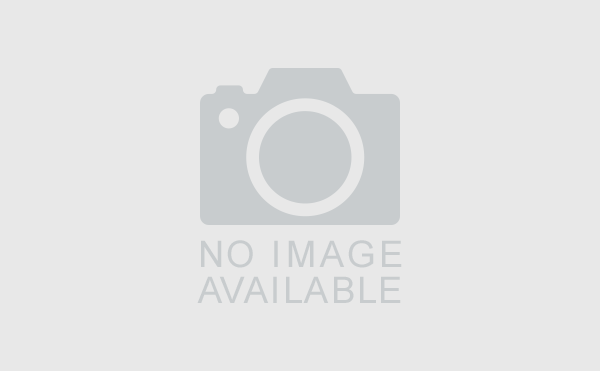不妊治療を考える 血液・ホルモン検査
女性のからだは、脳からの指令をホルモンが卵巣や子宮に伝え、妊娠の準備をします。
ホルモンの分泌が正常であれば、卵巣や子宮も正常に機能しますが、ホルモンの分泌に問題が
あると排卵や受精卵の着床に障害が起こり、不妊の原因になります。
妊娠に関わるホルモンは、月経周期により分泌されるホルモンの種類や量が異なるため、検査は
月経期と黄体期の二回行います。
尚、排卵日を予測するときなどは、尿からホルモン値を測定することもあります。
<卵胞刺激ホルモンの検査>
卵巣の機能を維持したりする働きがあります。
そのため、分泌量が少ないと卵胞が育たないなど「排卵障害」の原因になります。
<卵胞ホルモンの検査>
卵胞ホルモン(エストロゲン)は、卵胞が育つときに卵巣から分泌されるホルモンで、着床に
備えて子宮内膜を厚くする働きがあります。
また黄体期にも分泌され、黄体ホルモンとともに子宮内膜を整えます。
そのため、検査は月経期と黄体期の二回行われ、月経期には卵巣機能の状態を、黄体期には
黄体機能不全の有無などを調べます。
<黄体化ホルモンの検査>
黄体化ホルモン(LH)は、脳の下垂体から分泌されるホルモンで、排卵を促したり、黄体の活動を
維持する働きがあります。
そのため、このホルモンの分泌量が少ないと排卵がうまくいかないなど、「排卵障害」の原因になります。
黄体化ホルモンは排卵直前に大量に分泌(LHサージ)され、尿中にも検出できます。
そのため、排卵日を予測するときは、尿を採取して調べるのが一般的です。
<黄体ホルモンの検査>
黄体ホルモン(プロゲステロン)は、排卵後に卵胞が黄体に変化して卵巣から分泌されるホルモンで
子宮内膜を着床しやすい状態に整えます。
そのため、この分泌量が少ないと、子宮内膜が十分に成熟しない「黄体機能不全」と診断され、
着床障害の原因になります。
<プロラクチンの検査>
プロラクチンは乳汁の分泌を促すホルモンで、月経周期に関わらず検査が可能です。
分泌量が多いと「高プロラクチン血症」と診断されます。
この他に、男性ホルモンの分泌量も調べます。